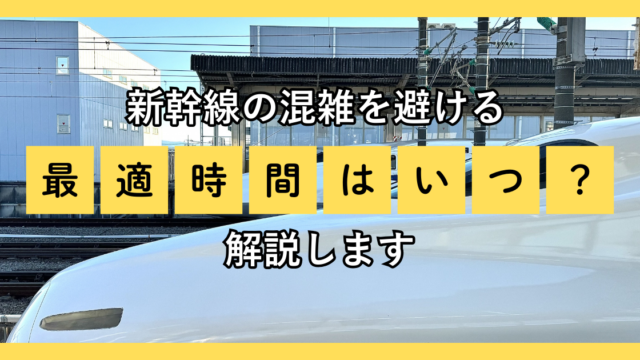最近では地球温暖化による異常気象もあってか、
ゲリラ豪雨が増えてきています。
今では一般的に使われている「ゲリラ豪雨」という言葉。
2008年の新語・流行語大賞で
トップ10入りまで果たしていますが、
実は正式な気象用語ではありません。
ゲリラ豪雨は集中豪雨の一種であり、
突発的で天気予報による
正確な予測が難しい局地的大雨のことです。
気象用語で近い言葉を探すのであれば、
「局地的大雨」や「集中豪雨」などと
言い換えることができます。
「局地的大雨」と「集中豪雨」の違いは、
雨の量や降り続く時間、その後に起こりうる影響の差で、
「集中豪雨」になると重大な土砂災害や
家屋浸水等の災害を引き起こすレベルの大雨になります。
気象庁は局地的大雨の原因として、
「積乱雲が同じ場所で次々と
発生・発達を繰り返すことにより起きる」
と説明しています。
ゲリラ豪雨とは何?

ゲリラ豪雨は集中豪雨の一種であり、
突発的で天気予報による
正確な予測が難しい局地的大雨のことです。
従来から使用されていたにわか雨や集中豪雨、
夕立といった言葉をマスコミなどが代用した表現で、
正式な気象用語ではありません。
気象用語で近い言葉を探すのであれば、
「局地的大雨」や「集中豪雨」などと
言い換えることができます。
気象庁によると「局地的大雨」は、
急に強く降り、数十分の短時間に狭い範囲に
数十mm程度の雨量をもたらす雨と定義されています。
「集中豪雨」は、
同じような場所で数時間にわたり強く降り、
100mmから数百mmの雨量をもたらす雨です。
「局地的大雨」は「重大な事故を引き起こすことがある」
というレベルであることに対して、
「集中豪雨」は「重大な土砂災害や家屋浸水等の災害を引き起こす」
とされています。
一般的に使われている「ゲリラ豪雨」ですが、
気象庁では大雨のレベルに応じて
「局地的大雨」と「集中豪雨」を使い分けています。
ゲリラ豪雨の原因とは?

先ほどゲリラ豪雨は気象庁では、
「局地的大雨」「集中豪雨」と
言い換えられると説明しました。
気象庁による局地的大雨の原因の説明について、
まとめるとこうなります。
「空気が上昇気流によって上空に押し上げられて、
雲が発生します。
上昇気流が強まり雲が成長を続けると、
積乱雲となり雨を伴うようになります。
積乱雲がさらに発達を続けることで、
狭い範囲に短時間で強い雨を降らせる原因になります。」
まとめ

ゲリラ豪雨は今でこそ一般的に使用されている言葉ですが、
実は正式な気象用語ではなく、
マスコミによって作られた言葉です。
気象庁では大雨のレベルによって、
「局地的大雨」や「集中豪雨」と言い換えられています。
ゲリラ豪雨は予測ができないので、
対策をするのはなかなか難しいですが、
ピークである7月~8月の時期は
特に気をつけたいですね。